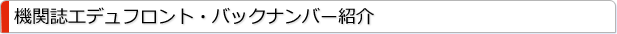サブタイトル
将来を見すえ、教育の課題に向き合う
特集内容
教育を取り巻く環境は大きく変化しており、多様化、複雑化する教育課題への対応
が必要となっている。
「教育シンポジウム in 東京2025」は、「将来を見すえ、教育の課題に向き合う」
を全体テーマとし、「総合プログラム」と「特設プログラム」で構成された。「総合
プログラム」では、学校において教科の主たる教材として位置付けられている「教科
書」をテーマとし、学びの連続性を生む教科書の活用の仕方や、教科書をベースとし
ながら教科書を超える学びを目指す授業設計について議論がなされた。また、「特設
プログラム」では、「学校における働き方改革」をテーマに、教職員の働きやすさ、
働きがいを高めていくための具体的な方策について議論がなされた。
目次等
総合プログラム 教科書の効果的な活用を考える
【基調講演①】
「教科書を活用して、教科書を超える学びへ」
市川 伸一 東京大学名誉教授
帝京大学中学校・高等学校 校長
【基調講演②】
「学びの連続性を生む教科書の活用」
秋田 喜代美 東京大学名誉教授
学習院大学文学部教育学科 教授
【トークセッション】
「教科書の効果的な活用を考える」
コーディネーター 市川 伸一
パネラー 奈須 正裕 上智大学総合人間科学部教育学科 教授
八木澤 史子 千葉大学教育学部 助教
南 英昭 文京区立第十中学校 校長
特設プログラム 学校における働き方改革 ~現状とこれから~
【講演】
「働きがいがあり、かつ働きやすい学校を広げる」
妹尾 昌俊 一般社団法人ライフ&ワーク 代表理事
OCC 教育テック大学院大学 教授
【トークセッション】
「学校における働き方改革 ~現状とこれから~」
コーディネーター 齋藤 等 東京成徳大学子ども学部 特任教授
パネラー 宮澤 一則 板橋区立中台中学校 統括校長
中村 めぐみ つくば市立みどりの学園義務教育学校 教頭
文部科学省学校DX戦略アドバイザー
二川 佳祐 練馬区立石神井台小学校 主任教諭
妹尾 昌俊
取材概要等
開催方法:オンデマンドによる動画配信
配信期間:令和7年3月10日(月)12:00~ 31日(月)20:00
主 催:公益財団法人 中央教育研究所
後 援:東京都教育委員会,茨城県教育委員会,
神奈川県教育委員会,群馬県教育委員会,
埼玉県教育委員会,千葉県教育委員会,
栃木県教育委員会,長野県教育委員会,
新潟県教育委員会,山梨県教育委員会,
株式会社時事通信社
協 力:株式会社学習調査エデュフロント,
東京書籍株式会社
内容紹介
(本文より)
予習→授業→復習という習得サイクルの学習を、学びの自己調整の視点から考えると、
すべての段階で教科書を活用することができます。予習では、教科書を読んで授業の見
通しをもつことができますし、教科書を読んだだけではわからなかった疑問について、
授業でしっかりわかるようになりたいと思って授業に臨むという姿勢が生まれます。授
業でも、教師が説明する中で、たくさんの図やわかりやすい記述など、教科書を最大限
に活用するとよいと思います。復習でも、知識を定着させるために、索引で用語を確認
するなど、教科書を活用することができます。
(市川)
一人1冊の教科書は、学校と家庭での学習をつなぐ架け橋となる大事なツールです。
それだけに、教科書を授業中にどう使うか、授業外・家庭でどう使うかの「連続性」が
とても大切だと考えています。授業中から授業外・家庭へ、学びの時間を延長し、学び
をつないでいくための指導が大切です。教科書をただ与えるだけではなく、子ども自身
が教科書を読み、活用できる学び手となるよう育てていくことが重要です。
(秋田)
既習の考え方の振り返りをうながすような学習を続けると、子どもたちは未習に際
し「必ず既習の中で使えるものがあるはずだ」という信念をもつようになります。既
習を生かして未習に挑むということが、見方・考え方を子どもに教えるということで
あり、転移可能な学力を身に付けるということだと思います。
(奈須)
教科書の効果的な活用について、小学校における事例を紹介いたします。
教科書を効果的に活用するとは、児童自身が教科書に書かれた情報を読み取り、課
題解決に取り組むことだと考えています。個別最適な学び、主体的・対話的で深い学
びが求められている今、課題解決に向けて必要な情報を児童自身が探し、取捨選択し
ながら内容を理解していくというような、教科書の読み方のスキルを身に付けること
が必要だと考えています。
(八木澤)
教科書をどのように使うかは手段で、目指すのは資質・能力の育成です。本校では、
市川先生の提唱されている「教えて考えさせる授業(OKJ)」に研究校として取り組ん
できました。(中略)OKJ自体が、基本的に教科書を中心に行う形になっています。
教師が教え、教えてから考えさせる展開に進むことを考えると、教える際に、ポイン
トとなる内容をどう押さえるかは、非常に重要だと思っています。単発の知識・技能
ではなく、次に生かせる汎用性のある知識・技能が身に付いているかどうか、理解確
認が大事です。
(南)
私は、Know HowよりもKnow Whoだ、とこの頃言い続けています。ある学校では、プ
リンタの前に、「○○ならお任せ」といった先生方のちょっとした自己PRを掲示して
います。このテーマだったらこの人に聞けばよい、とつながりができるように、
Know Whoを大事にするような職場づくりをしていただくと、結果的に負担軽減になり
ます。
(妹尾)
学校の働き方改革では、どのように働きやすく、働きがいがある学校にしていくか
が重要だと考えます。(中略)業務の見直しをしっかり行うとともに、教師の業務と
されている部分にもさらに切り込んで働き方改革を進めてほしいと思います。学校の
本来やるべきこと、学校がやっていくと楽しいこと、教師としてもやってみたいこと
などを充実させながら、それを支える環境整備を進めていく必要があります。学校教
育は社会全体を支える基盤だということを合意できるような風土改革も重要だと思い
ます。
(齋藤)
本校で取り組んでいる教科の融合化(コラボ授業)についてご紹介します。(中略
)面白かったのは、体育と数学のコラボ授業です。まず、何も条件を出さずに生徒に
校庭を10周走らせて、1周ごとのタイムをグラフにさせた後、「体力をまんべんなく
使うにはどうしたらいい?」と問いかけます。子どもたちは「グラフが一直線になる
のがいいだろう」、「比例だね」というところまで気付くので、自分のタイムでは1
周何秒で走ったらよいかを計算させてから、もう一度走らせます。そうするとほとん
どの生徒のタイムがアップしたのです。
(宮澤)
先生方の本来の仕事は、原石である子どもたちをきらきら輝かせるために、いろい
ろスキルアップしたり、対応したりすることです。先生が最高のパフォーマンスを発
揮できるようにするには、国、地域、行政機関が一体となって働き方改革に取り組む
しかないと思っています。
(中村)
本校では2023年7月から働き方改革を少しずつ進めてきました。(中略)途中で駄
目になったプロジェクトや、実際にやってみたらあまり効果がないとわかった取組も
あり、進めながら多くの学びを得ることができました。とにかく1回やってみよう、
駄目だったら戻せばいいよね、というマインドが醸成されたことが収穫だったなと感
じています。
(二川)
|